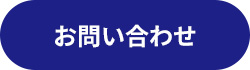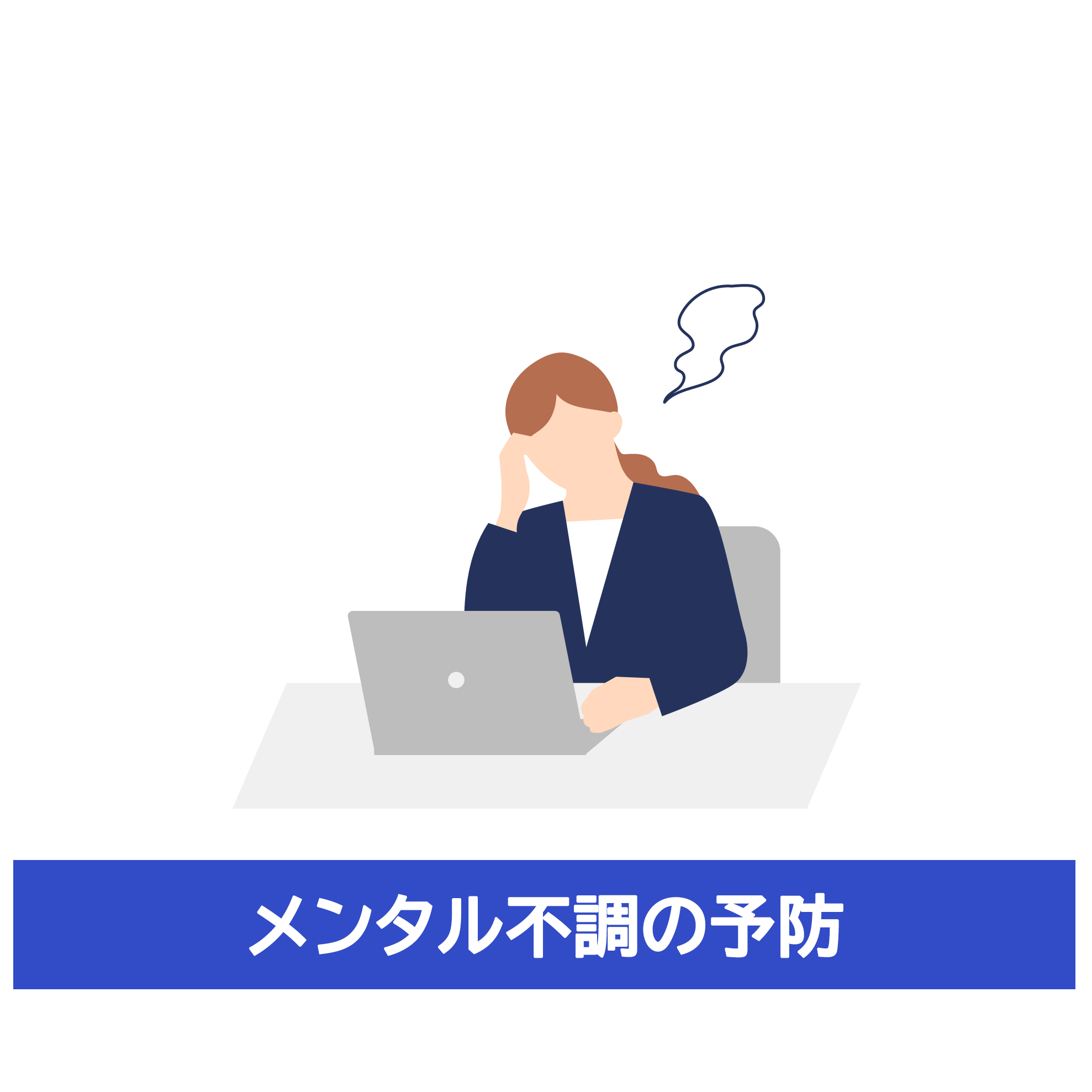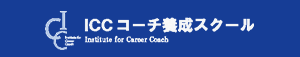心理的安全性、御社にも導入しませんか?
-若手育成・離職防止・チーム力向上・ストレス軽減-
現場の悩みを根本から解決する
「心理的安全性」の実践研修プログラム
心理的安全性とは?
「心理的安全性」とは、安心して意見を言える空気のこと
心理的安全性とは、メンバーが自分の考えや気持ちを、恐れることなく自由に話せる状態のことです。
「こんなこと言ったらどう思われるか」「怒られたらどうしよう」と不安を感じながら働く職場では、本音が言えず、改善のアイデアやミスの報告も滞りがちになります。
心理的安全性が高い職場では、意見やフィードバックが活発になり、チームの信頼関係が深まり、成果にも直結する好循環が生まれます。
米Google社の「プロジェクト・アリストテレス」でも、最も成果を上げるチームの共通点は「心理的安全性の高さ」であることが報告されています。
現場で求められる心理的安全性
心理的安全性が低い職場で起きていること
- 意見交換が少なく、メンバーが黙ってしまう
- ミスの報告が遅れ、トラブルが大きくなる
- フィードバックが形だけで、行動につながらない
- チーム内の対立や不信感が放置されている
- ストレスが蓄積し、メンタル不調が表面化している
このような状態が続くと、チームの雰囲気は悪化し、業務効率も低下します。
さらに、信頼関係が失われることで、離職率が上がり、組織の持続的な成長にも悪影響が及びます。
健康経営・働き方改革との関係
心理的安全性は、健康経営・働き方改革の土台となる
心理的安全性は、単に「話しやすい職場づくり」ではありません。
経済産業省が推進する「健康経営」や「働き方改革」の目標――すなわち、社員の健康維持や多様な働き方の実現を支える“土台”となる要素です。
これらすべてにおいて、心理的安全性の向上が大きなカギとなります。
「制度を整えただけで、職場は変わらない」――そんな課題を感じている企業こそ、この研修が役立ちます。
健康経営優良法人・えるぼし・くるみん・ホワイトマークなど、
認定済み/申請予定の企業に特におすすめです
この研修は、健康経営や働き方改革に取り組む企業・病院にとって、各種認定制度の取得にもつながる実践的な内容です。実際に導入された組織では、メンタルヘルス対策や若手定着など、さまざまな効果が得られています。
※本研修は各認定の取得・更新そのものを保証するものではありません。申請書類や取組報告書の「補強資料」としてご活用いただけます。
健康経営優良法人認定制度
(所管:経済産業省)
-
該当項目
4-(1)ラインケア
5-(2)職場コミュニケーション促進 -
研修によって得られる効果
管理職の関わり向上
職場のメンタルヘルス環境整備 -
活かせるポイント
・管理職・チーム全体でのヘルスリテラシー向上
・心理的安全性が高まることでストレスチェックの結果にも改善傾向
・休職・離職予防につながり、健康経営の基盤を支える
えるぼし認定<女性活躍推進法>
(所管:厚生労働省)
-
該当項目
③労働時間等の働き方
⑤多様なキャリアコース - 研修によって得られる効果 女性職員の活躍・定着支援につながる
-
活かせるポイント
・多様な価値観を尊重する風土づくりに直結
・女性管理職の育成や発言機会の均等化を後押し
・安心して意見を出せる文化がキャリア支援の土台となる
くるみん認定<次世代育成支援対策推進法>
(所管:厚生労働省)
-
該当項目
育児中社員への支援体制
働きやすい職場風土 - 研修によって得られる効果 育児中職員も安心して働ける風土づくり
-
活かせるポイント
・育児中の職員も安心して働けるチームづくり
・心理的安全性により上司や先輩に相談しやすくなり、職場復帰・両立支援が円滑に
・OJTや育成面での信頼形成がスムーズになり、育成負荷の軽減にもつながる
ユースエール認定<若者雇用促進法>
(所管:厚生労働省)
-
該当項目
若者の定着率
研修制度の充実 -
研修によって得られる効果
若手への支援力向上
育成環境の改善 -
活かせるポイント
・若手職員が安心して意見や相談ができる職場環境づくりに直結
・入職後の早期離職を防ぎ、定着率の改善に貢献
・キャリア面談・成長支援制度との連携で、職場全体の人材育成力を強化
ホワイトマーク<労働安全衛生優良企業公表制度>
(所管:厚生労働省)
-
該当項目
メンタルヘルス対策
安全文化の形成 - 研修によって得られる効果 安心して報告・相談できる組織へ変革
-
活かせるポイント
・ヒヤリ・ハットの報告が増え、安全文化が強化
・現場の声を拾いやすくなり、労災リスクの未然防止に貢献
・メンタルヘルス対策とも連動し、組織全体の安心感が向上
だから――
- エビデンスづくりに役立つ
研修前後で心理的安全性スコアを測定し、チームの現状を「見える化」。
アンケート→診断→ディスカッション→アクションプランへとつなげるプロセスが、改善策立案や認定申請書類の補強資料作成に寄与します。 - 複数認定取得・更新への取り組みを後押し
本研修は「健康経営」「働き方改革」「安全衛生」の観点を横断的に扱うため、若手定着や女性活躍、メンタル対策など複数の評価項目への対応を後押しします。えるぼし・くるみん・ユースエール・ホワイトマーク等を目指す企業・病院に有効な選択肢となり得ます。 - 更新審査で求められる“継続改善”の裏付け資料として活用可能
単発で終わらず、年次フォローや簡易診断付きプランも選択できるため、PDCA の継続的実践をサポート。その成果レポートは、更新審査で求められる「継続改善」項目の裏付け資料として活用いただけます。
研修の特徴と目的
「知る」だけでは終わらせない。現場で“使える”心理的安全性へ
本研修では、心理的安全性という言葉の理解にとどまらず、現場での実践・行動の変化につなげることを目的としています。
参加者は自身のチームや部署の状況を見つめ直し、心理的安全性を高めるための具体的な関わり方を学びます。そして、研修の最後には現場で即活用できるアクションプランを作成します。
研修で得られる4つのステップ
① 心理的安全性の本質と必要性を理解する
② 自部署の状態を診断し、現状を可視化する
③ 対話・承認などのコミュニケーションスキルを実践的に学ぶ
④ 自チームで活用するための具体的な行動計画を立てる
講義を一方的に聞くだけの研修ではありません。
グループワークやペア対話を通じて、自ら「気づき」「考え」「言葉にする」プロセスを重視しています。
研修プログラム
心理的安全性は、単なる知識習得では身につきません。
本研修では、参加者が自ら体感し、気づき、行動につなげる参加型の設計になっています。
以下は、1日(6時間)の研修例です。
具体的な研修内容(6時間の場合)
- 心理的安全性の基礎
講義による心理的安全性に関する基本情報の理解 - 心理的安全性診断
弊社オリジナルの心理的安全性診断を行い、その結果をもとにグループディスカッションを行う。その中で自組織の課題やめざす方向性を見出す - 心理的安全性向上のためのアクションプラン
実際に自分がめざす心理的安全性が高い職場になるには、何をすべきなのか具体的な行動計画を立てる - 心理的安全性を高めるトレーニング
①ファシリテーション
意見が分かれている会議の進め方
②コミュニケーション
信頼関係を築く聞き方、相手が受け取りやすい伝え方、新人・若手が居場所を感じられるほめ方
③アクションプラン実践のためのコーチング
コーチングによって研修後の行動計画(誰に対し、何を、いつまでに行うのか等)を明確にして実行につなげる
期待される効果
心理的安全性が高まることで、職場は目に見えて変わります。
本研修を通じて、次のような効果が期待できます。
-
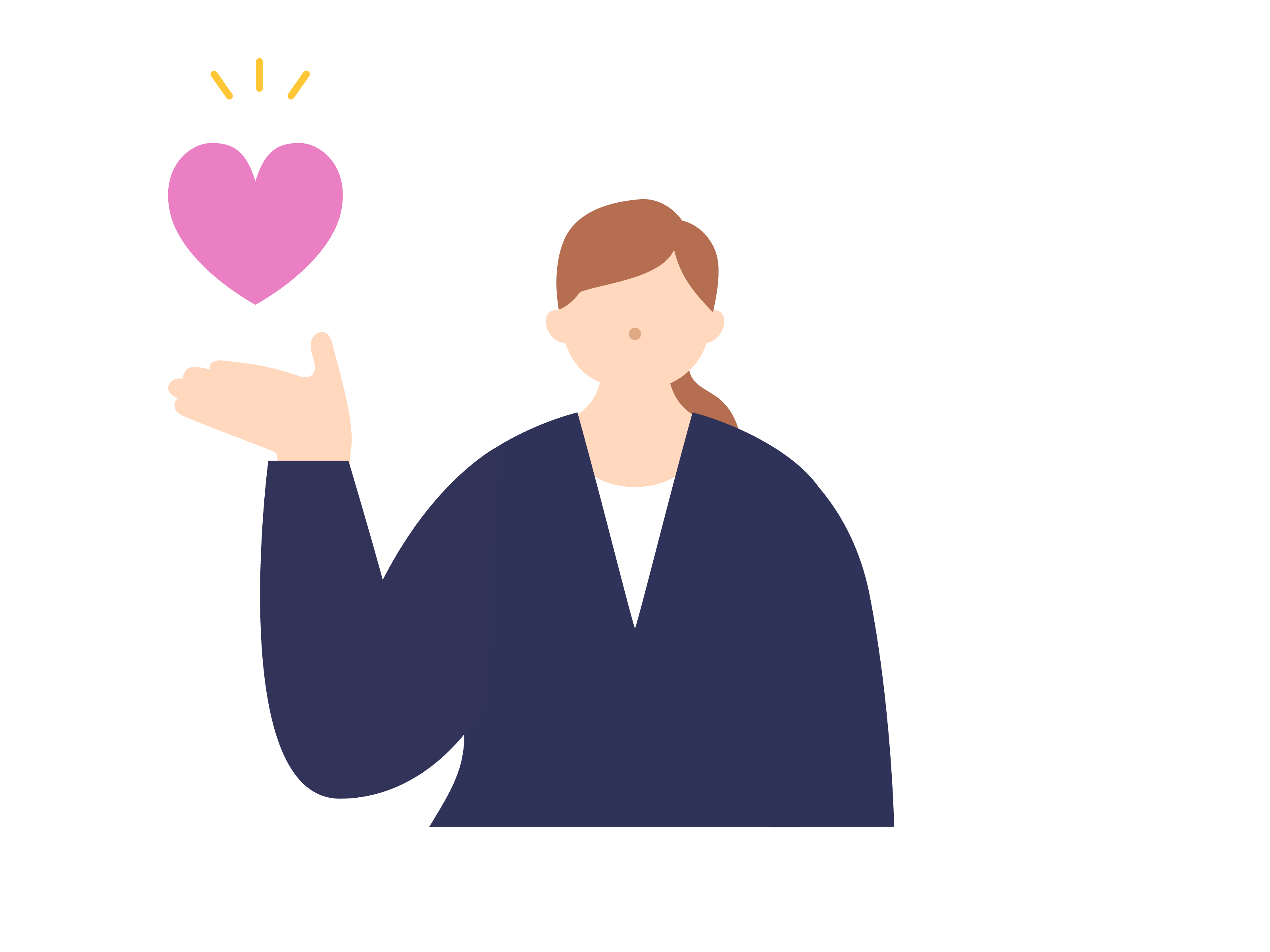
メンタルヘルス向上
社員が安心して意見や懸念を共有できる環境が整うことで、ストレスが軽減され、精神的な健康が向上することが期待できる
-

チームワークの強化
オープンなコミュニケーションが可能な職場では、社員間の信頼が深まり、協力しやすくなり、チーム全体のパフォーマンス向上に寄与する
-

業務の効率化
心理的安全性が高まることで、社員は失敗を恐れず新しいアイデアや改善策を提案し、業務の効率や質が向上することが期待される
-

リーダーシップの強化
リーダーが部下の意見を尊重し、支援することで、信頼関係が構築され、部下の成長を促し、リーダーシップ能力が高まる可能性がある
-
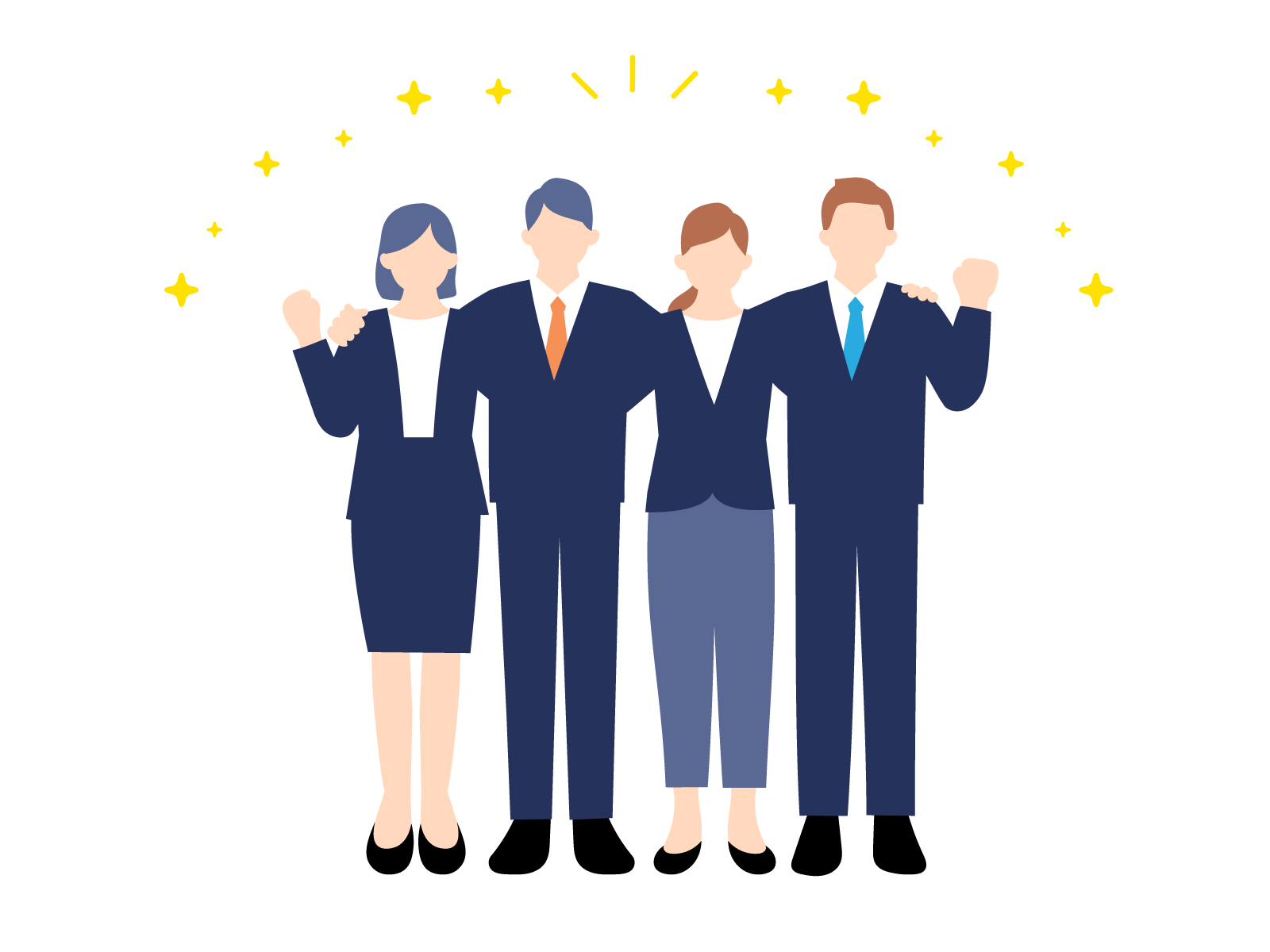
組織の定着率向上
心理的安全性が確保されることで、社員は安心して働ける環境が整い、向上する傾向が報告されている。また、新規採用にも良い影響を与える
-

業績向上
社員が自分の意見を自由に出せる環境が整うことで、問題解決のスピードが早まり、業務の質が向上し、最終的な業績向上の土台づくりに寄与する
※上記は一般的に報告されている効果であり、実際の成果は組織の状況や施策の継続性によって異なります。