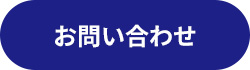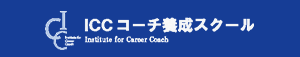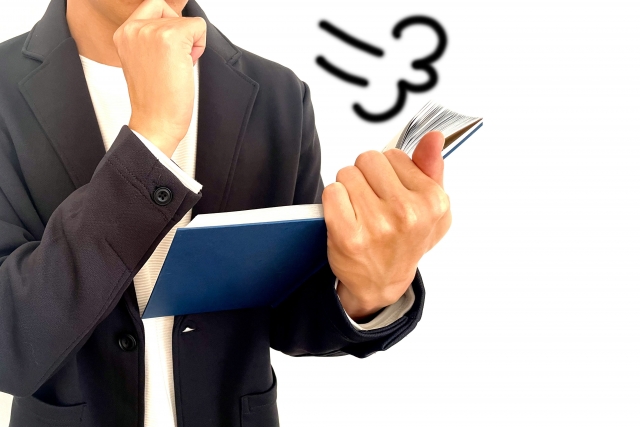
「俺の若い頃はさ…」「最近の若者は…」
そんなひと言、何気なく口にしていませんか?
それ、もしかしたら「グレーハラスメント」かもしれません。
今、パワハラやセクハラとまでは言えないけれど、受け取る側が不快に感じる「グレーゾーンのハラスメント」が、
職場の空気をじわじわ蝕んでいると言われています。
たとえば――
・ため息や舌打ち、あいさつを返さない態度
・「あなたのためを思って」 と一方的にアドバイス
・過去の価値観に基づく決めつけの発言
・プライベートに土足で踏み込む質問
こうした言動に、「あの人に悪気はない」と受け流してくれる部下もいるかもしれません。
でも、最近の調査では、不快な言動を受けた人の約46%が「退職を考えた」と答えています。
特に、「無視・仲間外れ」「飲み会の参加強制」では、約7割が退職を検討していたというデータもあります。
実は、このグレーハラスメントの厄介なところは、本人が「良かれと思ってやっている」ケースが多いこと。
悪意がない分、気づきにくく、改善されにくいのです。
とはいえ、部下が「言い返せない」「受け流すしかない」立場である以上、
職場の空気はどんどん居心地の悪いものになっていきます。
気がついたときには、若手が次々と辞めていく…なんてことも。
では、どうすればいいのか?
まずは、「言葉の受け手は相手」という視点を持つこと。
上司としての正論や善意が、必ずしも部下の心に響くとは限りません。
大切なのは「どう受け取られたか」を想像すること。
自分の過去の経験や価値観が基準になっていないか、立ち止まってみましょう。
また、社内で「何がNGか」を曖昧にしないことも大切です。
グレーゾーンハラスメントを防ぐための明確なガイドラインや、相談しやすい体制づくりも、企業として急務です。
世代間ギャップは、避けて通れません。
だからこそ、「お互いに不快にならない伝え方」を、組織として磨いていく必要があるのではないでしょうか。
時代は変わっています。リーダーの言葉も、変わっていきましょう。