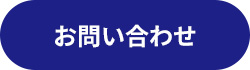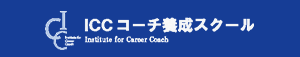ある朝、若手社員との待ち合わせに「8時10分前に集合ね」と伝えたところ、彼がやってきたのは8時8分。
内心「え、遅刻では?」と思ったものの、彼はきょとんとした顔。
一体なぜこんな食い違いが起きるのか…
実はこれ、世代間ギャップの典型例なのです。
昭和世代にとって、「8時10分前」は「8時の10分前」、つまり「7時50分」。
ところが、令和世代の多くは「8時10分の前」、つまり「8時~8時9分の間」だと理解するのだとか。
ある調査では、40~50代の84%が「7時50分」と答えたのに対し、
10代~20代では「8時台」と答えた人が64%もいたという結果も。
なぜこんな違いが?
このギャップの背景には、スマホの存在があります。
今の若者たちは小さい頃から正確なデジタル時間に触れてきたため、
1分単位で到着時間を調整できる環境が当たり前。
そのため、「10分前集合」という曖昧な言い回し自体、馴染みがないのです。
このようなズレは、待ち合わせだけではなく、日常の指導場面にも影響します。
たとえば、「できるだけ早めに仕上げて」と言えば、
上司の期待は「今日中」、でも若手の認識は「今週中」かもしれません。
曖昧な表現は、すれ違いのもとになりやすいのです。
では、どうすればこのギャップを埋められるのでしょうか?
ポイントは、「伝えたつもり」ではなく、「伝わったかどうか」を確認することです。
指導の際は、具体的な時刻や期日、行動内容を明確に伝えること。
たとえば、「◯日◯時までに」「このフォーマットで」など、曖昧さをできるだけなくすことが重要です。
そしてもう一つ大切なのは、令和世代が間違っているのではなく、
「そう受け取ってしまう背景がある」「世代によって前提が違う」と理解すること。
「早めに来てね」ではなく「7時50分に来てね」、
「できるだけ早め」ではなく「○日の○時まで」と具体的に伝える。
この一言で誤解は防げます。
上司と部下のすれ違いは、小さな誤解から始まることも多いもの。
世代間ギャップは避けられなくても、工夫次第で埋めることはできます。
相手の視点に立って伝える力こそが、令和世代の育成には欠かせません。
参照:『令和の若者は「8時10分前に集合」で8時8分に来る!?なぜ「7時50分」ではないのか?衝撃の世代間ギャップの理由』