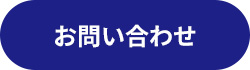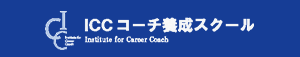先日、ある研修で中間管理職の方からこんなご相談を受けました。
「部長が全員のゴミを集めて捨ててくださっていたんです。慌ててお手伝いしたのですが、新人は見て見ぬふり。
こういうことを新人に求めるのも、もう時代じゃないんですかね…」
確かに、Z世代の若手社員は「効率」を重んじ、意味の見えない行動や“形だけの気遣い”を嫌う傾向があります。
しかし、それは決して協調性がないということではありません。
むしろ、「何のためにやるのか」が分かれば、自分なりの工夫で動ける世代です。
ここで大切なのは、「心理的安全性」の確保です。
上司や先輩が何かを率先して行っているときに、「手伝わないと評価が下がるのでは」「余計なことをして怒られないか」と不安を感じて動けない新人もいます。
見て見ぬふりに見えても、実は「どう振る舞うのが正解か分からない」だけかもしれません。
――管理職・リーダーができることは何か?
①行動の理由を言葉にする
「部長がゴミを集めてくれているから、一緒に協力しよう」と目的を伝える。
②率先垂範を見せる
上司自身が自然に動く姿を見せることで、「動いていいんだ」という安心感を与える。
③効率性と意味づけをセットにする
「こうすれば片付けが早く終わるね」「業務に集中できるよ」と、Z世代が納得できる理由を示す。
“効率を重んじる”という価値観は、組織にとって大きな武器になります。
ムダを嫌う視点を活かせば、業務改善のアイデアも生まれるでしょう。
ただし、その力を発揮するには「余計な失敗を恐れず発言・行動できる」心理的安全性が不可欠です。
ちょっとした声掛けや説明が、新人を“傍観者”から“自発的な協力者”へ変えます。
Z世代の価値観を否定するのではなく、組織の成長エネルギーに変えていきましょう。